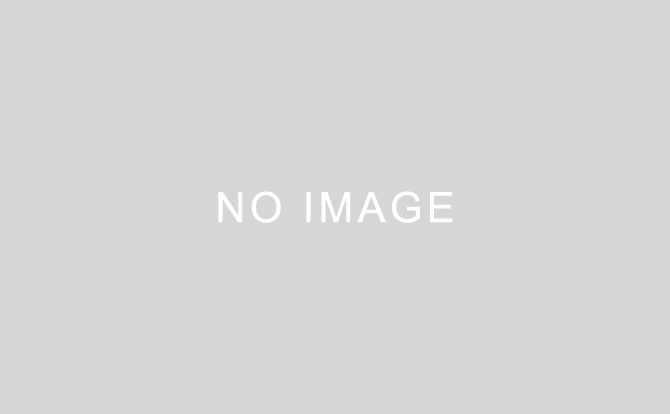映画『窓ぎわのトットちゃん』を観てきた。
正直、観るつもりは全く無かった。
予告映像を見た印象では「ヘテロラブロマンスを匂わせる子どもの友情を描いた作品でしょ?」と思ったし、キャラデザも好みではなく、むしろ「ヘテロラブロマンスを匂わせる子どもの友情」を描いている(ように見える)限りは顔や体の一部が妙に紅潮した表現は気持ち悪く感じた。
しかし、観た人の評価が軒並み高く、「じゃ、まぁ行ってみるか」と心を入れ替えて観に行ってみた。
結果、観てよかったと心から思っているので、せっかくだから感想文を書いてみた。
まず、作画が素晴らしい。
アニメをあまり観ない私でも、始まってすぐ作品性の高い映画であることがわかる。
背景が美しく、毎秒絵画を観させられているようで眼福。
作品内で3箇所現れるイメージシーンも、それぞれが魅力的で、芸術的で素晴らしい。
随所で描かれる動植物は色やタッチが美しく、対して終盤に登場するB29は妙にギラギラしていて存在の異様さが際立っていた。
※これ以降は物語の内容に触れますので、ネタバレを気にする方は読まないでください※
物語についていえば、予告映像で私が感じた「ヘテロラブロマンスを匂わせる子どもの友情」は、全く無いわけではないのだが、あくまで作品の一部であり全面に押し出されているわけではない。
子どもの視点で戦争を描いた反戦映画だ。
それゆえ気になっていたキャラデザも、むしろ生き生きとした生命感や子どもの純粋の表現に感じた。
私が子どもの頃に観てきた戦争関連の映像(創作も含め)は、空襲のシーンなど直接的に戦闘を想起させるものが多かったように感じるが、この作品はあまり残酷なシーンは無い。
いや、「無い」は適切な表現ではないか。
作り手の「どうだ、戦争とは残酷だろう」みたいな意図が見えるシーンが無いというか、直接的な表現や説明は避けられている。
例えば、駅員のおじさんがある日、女性に代わっているシーン。
トットちゃんも「あれ?」という表情をするのだが、なぜ女性に代わったのかの説明などは一切ない。
太平洋戦争の開始とその戦況が悪くなっていくにつれて社会がどんなふうに変わっていくのかを、鑑賞者も追体験する形で知らされていく。
英語の看板を日本語に直した喫茶店、お金を入れても出てこないキャラメルの自販機、軒先に落ちている愛犬ロッキーの首輪、子どもたちの描く絵も戦争の絵に変わる。
戦争の表現で特に印象に残ったのは、同級生の泰明ちゃんの死に触れて、トットちゃんが駆け出していくシーン。
身近な人間の死をきっかけに、この社会にはすでに戦争による死や苦しみが溢れていること、そしてその死や苦しみは、それを引き起こしている戦争の熱狂によって見えなくされていること。
走る姿が、突然自分の前に立ち現れる現実に混乱する心情を感じさせる。
戦争をこんなふうに描けるのかと、演出力に脱帽した。
ラストシーンは、なんとなくフワっといい感じの表現を持ってきたようにも見えて、観た直後はどのように捉えていいのかわからなかった。
時間が経って感じたことは、黒柳徹子へのリスペクト。
チンドン屋の幻影は、苦しい状況の中でもトットちゃんの想像性が失われていないことを、幼い妹を抱く姿には、周囲の大人から受け取った愛を、他の人に分け与えられる優しさや愛情深さを表現していたのでは無いかと思う。
それは、テレビ女優第一号として長きに渡り日本のエンターテイメント界を牽引してきたこと、ユニセフ親善大使などの活動を通して、弱い立場の人たちに寄り添ってきたことなどに繋がっている。
また、そんなトットちゃんの姿を通して、困難な状況にあっても、その人が持つ価値は失われないというメッセージを込めたのでは無いか。
本作の企画が始まったのは2016年。制作は2019年に開始したそうだ。
その間には、ロシアによるウクライナ侵攻、イスラエルによるガザへの空爆などが起きた。
まさか、社会の変化によって、こんなにも作品の持つ意味が大きくなってしまうとは、製作陣も予想だにしなかっただろう。